特許調査は、単なる検索作業ではなく、技術と戦略をつなぐ出発点だ。
本連載「特許調査の歩き方」では、ベテラン弁理士・角渕由英と若手研究者出身の土本晃久が、対話を通して調査の本質に迫る。
第1回は「特許調査ってなに?」。二人の出会いを軸に、調査がもたらす価値と、“良い調査“の考え方を探る。
<特許調査との出会い>
 土本
土本角渕さんは特許調査に強いサーチャー弁理士として活躍されていますが、特許調査との出会いはどんな形だったのでしょうか?



最初のきっかけは大学院時代です。2008年の春、研究室で教授から「特許があるか調べておいて」と言われ、当時の特許電子図書館(IPDL)で検索を始めたのが、特許との最初の出会いでした。



論文を調べることはもともと好きでしたし、計算やデスクワークの方が性に合っていたので、特許文献も自然に読み込むようになりました。その過程で、弁理士という職業を知り、研究成果が出願書類へと形になっていくプロセスに強く惹かれたことを覚えています。
角渕の知財キャリアの始まりについては、2020年1月の知財ぷりずむ 新春特別寄稿の冒頭に詳細に述べています。



その後、サーチャーとしてのキャリアはどのように始まったのでしょうか?



博士課程の後、登録調査機関でサーチャーとして勤務しました。2011年から2016年まで、化学系を中心に幅広い技術分野の調査に携わり、毎日のように特許を読み、検索式を工夫し、先行技術の位置づけを整理する仕事を続けました。



案件の量とフィードバックの機会が多く、調査の基本と応用を実務で徹底的に鍛えられた時期です。その経験が、いまの“検索で終わらせず、意思決定に効かせる”という姿勢の土台になっています。



土本さんはベンチャーキャピタル(VC)在籍時に特許調査に興味を持ったんですよね?



はい。スタートアップへの投資判断のために、スタートアップが持つ特許の調査を行ったのが最初でした。自分で調査することに限界を感じて専門家へ依頼したところ、それまでの調査では見つからなかった重要な文献を新たに発見することができました。調査によって、投資の意思決定を左右する重要な情報を得ることができ、スタートアップにとっても研究開発の指針となったようでした。



調査がもたらす価値の大きさを実感したことで、知財業界に入ったと言っても過言ではありません。
キャリア選択の理由については、土本のnote、新卒VCを辞めて、知財業界に飛び込んだ理由に詳しく述べています。
<特許調査とは何であるか?>



角渕さんも私も、ある意味「調査」が入口だったわけですが、業界としては「出願・権利化」が主要な業務というイメージもあると思います。知財業務全体において特許調査がどのような位置付けなのか、教えて下さい。



確かに出願をして権利を確保することは大事です。しかし本当に重要なのは、その特許の権利化によって事業上の優位性を生みだせることです。



そのためには、調査によって当該技術分野の動向や、強い特許を取るためのポイントを把握した上で、それらを踏まえた戦略を立てる必要があります。



特に初期のスタートアップなどでは、資金調達や共同研究に先立って「まずはとにかく出願」となりがちです。Moat形成の観点では、そもそも特許的な競合企業がどこで、どのような権利で参入をブロックするのかといった目的意識が重要ですね。



はい。特許調査を含む知財実務、知財そのものは手段に過ぎず、それ自体が目的ではありません。出願などのアクションには必ず事業上の目的が伴うはずです。



例えば競合他社の模倣防止や、開発方針の策定、自社製品の法的リスクの緩和などです。目的に応じて先行技術調査、侵害予防調査、無効資料調査といった調査の型を使い分けるほか、複数の観点で調査を実行することもあります。



調査によって、例えば、権利を取るメリットより情報公開のデメリットが大きいと判断すれば、出願を勧めないこともあります。



なるほど。とは言え、言うは易しで、特許の活用の場面を想像しながら実際に判断を下すのは難しそうな気もします。どのようにそのスキルを身につけていくのがいいでしょうか?



出願、中間対応、他社特許への無効化などの対応、係争など、幅広く知財業務に触れることをおすすめします。



活用の場面での勘所が掴めれば、逆算して有効な出願や調査に繋げることができるようになります。良い調査をするためには、逆説的ですが、調査以外のこと、調査の後工程の実務をするのが重要です。



この点に関して、グローバルブレインの廣田さんがXで『特許実務でもう一つ大事なのが後工程のフィードバックを回すこと出願業務は中間対応や海外対応することで成長できるし、他社特許の対策や係争業務の経験は中間対応に活かせます。出願業務だけだとすぐに良し悪しが見えにくいので、早めに後工程を経験するのが近道だと思います。』と述べていましたが調査業務でも同様のことがいえると思いました。
<良い調査とは?単なる検索に留まらない可能性>



特許調査の具体的な内容についても聞いたいです。調査といえば、データベースを用いた検索がまず思い浮かびます。角渕さんは特許検索競技大会2017で最優秀賞を受賞し、現在は委員長も務めていらっしゃいますね。



はい。キーワードと特許分類を駆使した検索式によるデータベース検索は、特許調査において非常に重要です。しかし、「調査=検索」だとは考えていません。



それはなぜでしょう?



検索というと、なんとなく近いものを探すようなイメージがありますが、それでは不十分です。調査の目的に応じて、探したい文献の姿を事前にイメージする、或いは、実際に手を動かす中で解像度を高めることで、「ただ近い」技術ではなく、「使える」文献を探す必要があります。



例えば、侵害予防調査ではオールエレメントルールを意識する必要がありますし、無効資料調査では主引例と副引例との組み合わせを意識する必要があります。



目的を意識した検索自体の設計、調査の戦略立案が重要です。



単に近い技術の文献リストだけ出てきても、何かの意思決定に活用するのは難しいですね。検索の意図についての依頼主とのコミュニケーションも重要そうです。



依頼主の困りごとを丁寧に聞いた上で調査を行い、報告では、検索式の構成を噛み砕いて説明したり、チャートを作成して分かりやすく示すことを心がけています。無効主張や侵害判断などのロジックから遡って説明することもあります。



検索の目的を正しく設定するには、技術理解と法律理解、両方とも重要そうですね。



その通りです。技術理解に関しては、最近であれば生成AIを活用することで効率化が可能です。生成AIに調査中の分野に関する技術常識をまとめさせたり、特許文献の簡易的なスクリーニングができたりします。Web上の製品情報など非特許文献の調査に強いのも特徴です。検索に留まらず、目的第一でツールを組み合わせることが、今後より重要になるでしょう。
第1回は、特許調査ってなに?と言う観点でお話をしました。
第2回は、特許調査をやってみようというテーマで、手が躓きやすいポイントと克服手段、キーワード選定、分類記号、データベースの使い分けについて話しをしようと思います。


弁理士法人レクシード・テック パートナー弁理士・博士(理学)
特許調査と調査結果を踏まえた提案を得意としており、化学、医薬・バイオ、IT、機械など分野を問わず、これまでに数千件以上の調査を担当してきた。
出願権利化業務に加えて、調査業務、情報提供、特許異議申立、無効審判や特許権侵害訴訟の代理、知財コンサルティングも行っている。


弁理士法人レクシード・テック 特許技術者・博士(工学)
ベンチャーキャピタルにて主にディープテックスタートアップの投資検討、起業支援に従事した後、弁理士事務所へ特許技術者として入所。スタートアップの成長フェーズや事業モデルに適合した調査・分析の提案を行っている。
リチウムイオン電池、機械学習に関する研究テーマで博士課程を修了。化学・材料系を得意分野とし、生成AIを活用した調査の効率化にも取り組んでいる。

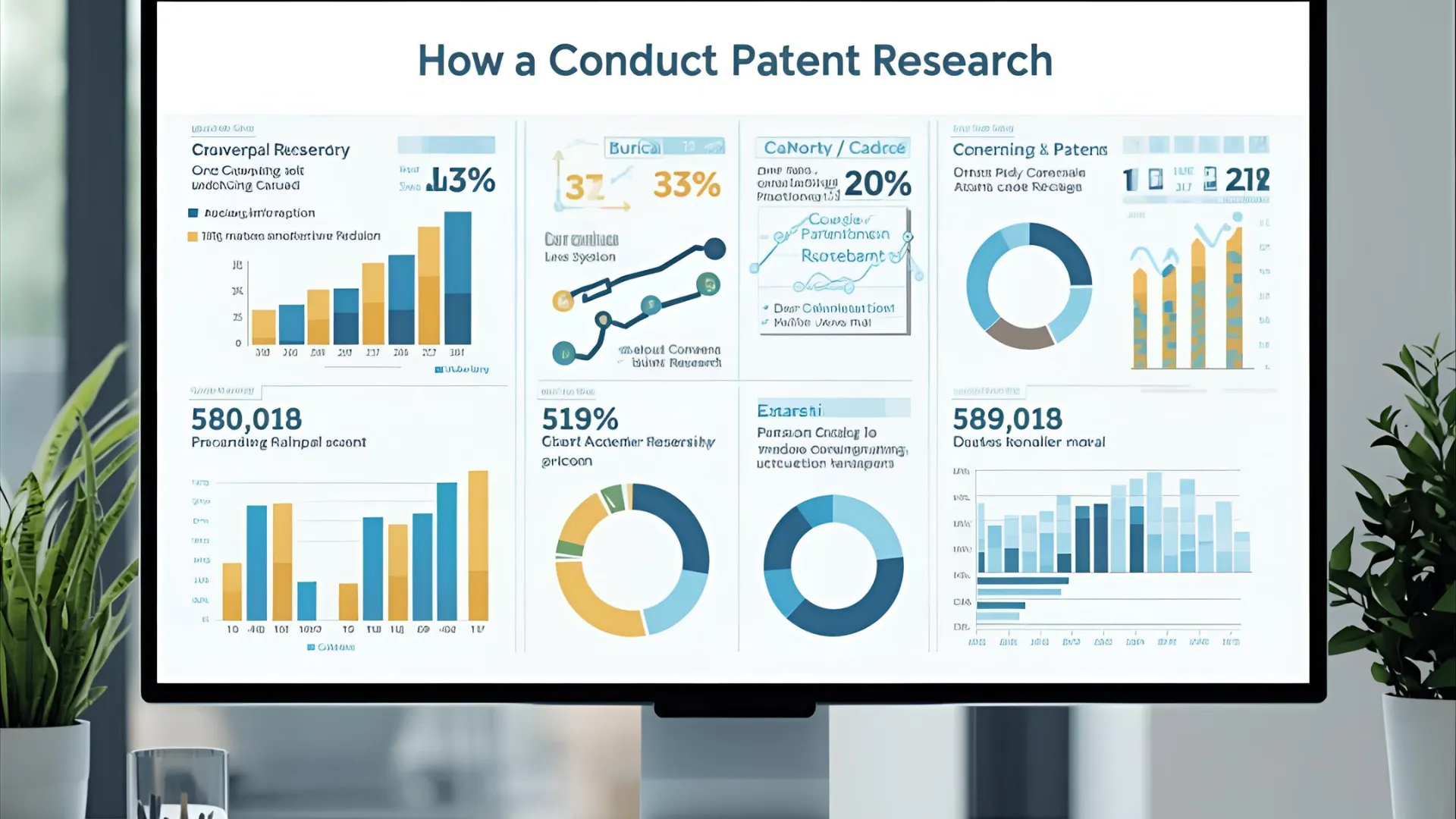
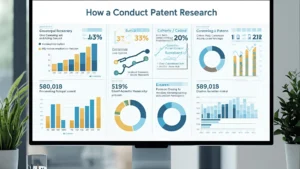
コメント