スタートアップ支援の現場から考える、生成AI時代における知財パーソンの新しい役割
はじめに
今日では、スタートアップを中心に新規事業を生み出す動きがますます活発になっています。社会課題の解決や新しい市場の創出を目指す企業が増え、大企業でも既存事業に依存せず新しい価値を自ら生み出すことが求められています。新規事業の創出は、もはや一部のスタートアップやベンチャー企業だけのテーマではなく、あらゆる組織にとって重要な経営課題となっています。
このような環境の中で、事業アイデアをいかに実現へとつなげ、他社に模倣されないように保護するかが重要です。特に、生成AIの登場により、事業構想のスピードが飛躍的に高まる一方で、知財のあり方も大きく変化しています。
本稿では、ふわっとしたアイデアを出発点に新規事業をどのように形にし、そしてそれを知財でどのように守るか、さらに生成AI時代における知財パーソンの新しい役割について考えていきたいと思います。
ふわっとしたアイデアの中に、事業の種がある
スタートアップの多くは、「こんな課題を解決したい」「こんな仕組みをつくりたい」といった抽象的なアイデアからスタートします。スタートアップを支援する知財パーソンは、まずその思いを丁寧にヒアリングするのが大事です。何を実現したいのか、どんな顧客価値を生みたいのか。そうした議論の中で、アイデアを構造化し、事業としての方向性を整理していきます。
同時に、事業上の競合と知財上の競合を分けて考えることも欠かせません。ビジネス上はまだ表に出ていない企業でも、その分野で特許出願を積み重ねていれば、将来的に大きな脅威になり得ます。特許情報を分析することで、スタートアップが気づいていない知財上のリスクを可視化していきます。
発明の芽は「ふわっとしたアイデア」の中に潜んでいます。課題を新しい手段で解決できるなら、それは特許になる可能性があります。経営者との対話を通じて、思いの中から発明を抽出し、広い権利につなげることが重要になってきます。
特許は未来への布石
スタートアップにとって、最初の特許は企業の信頼性を象徴する存在となります。プレスリリースや資金調達の前に特許出願を行っておけば、投資家へのアピールにもなります。ただし、出願や審査請求のタイミングは慎重に見極めなければなりません。早期審査を利用すれば短期間で特許を得られますが、早すぎる公開は競合への情報開示にもなります。「いつ出願するか」「どのタイミングでどの形式で審査請求をするか」も経営判断の一部となります。
特許出願を行いたいとスタートアップの経営者から相談があったときに、おおむね3回のミーティングを行います。1回目でビジネス内容を聞き取って発明の大枠を言語化し、先行技術調査を行います。2回目で調査結果をもとに出願戦略を議論し、特許明細書を作成します。3回目で作成した明細書を確認して出願に進みます。時間はかかりますが、この過程こそが、企業のアイデアを実際の権利として形にするプロセスとして重要になります。
生成AI時代に知財パーソンに求められる力
ChatGPTなどの生成AIが登場し、明細書の下書きや既存特許の要約などはAIでも可能になりつつあります。今後、生成AIが知財業務の多くを担う時代が来るのは間違いありません。しかし、AIができるのは文章を作ることであって、意味を作ることではありません。
知財パーソンが果たすべき役割は、単なる文書作成から、経営者やエンジニアの思考を整理し、発明の本質を言語化するコンサルティングへとシフトすると考えられます。生成AIを使いこなすことは必要ですが、それ以上に大切なのは、AIが導き出せない問いを立てる力です。テクノロジーが進化するほど、人が何を考え、どう判断するかが問われるようになっていきます。
若手へのメッセージ――知財の本質は対話にある
私は、知財の仕事は技術とビジネスをつなぐ架け橋であると考えています。法律を理解するだけでなく、経営者の夢や課題に耳を傾け、それを形にする力が求められます。若手の皆さまには、まず好奇心と対話力を磨いてほしいと思います。知らない分野に飛び込み、人と話し、発想を広げる。その積み重ねが、将来の専門性につながります。
AIの進化で仕事の形は変わっていきます。しかし、人と人が対話し、共に考え、新しい価値を生み出す――そこにこそ、知財の本質があります。ぜひ、変化を恐れずに自分の可能性を広げていただければと思います。知財の世界は、その挑戦を受け止める懐の深いフィールドですので。

IPTech弁理士法人 副所長/弁理士
株式会社クボタでの機械製品の品質向上・開発経験を生かし、DXやAI等、最新技術を活用した企業を中心に支援。コロナ禍以降、YouTubeなどのSNSを広く活用し、独自企画による知財コンテンツの情報発信や専門家コミュニティの形成に努める。
著書に「ふわっとしたアイデアからはじめる新規事業を成功させる知財活用法(中央経済社)」等。

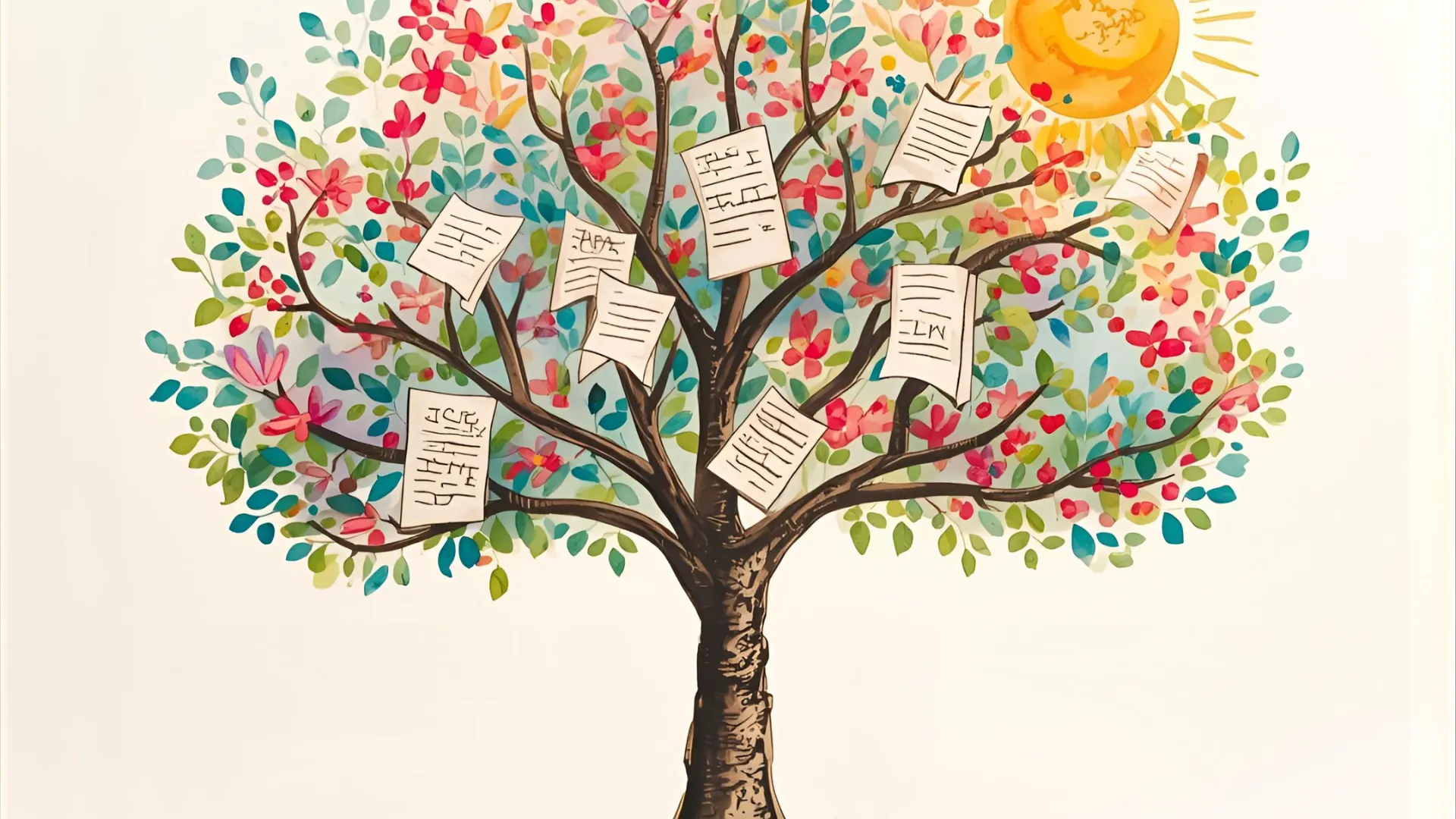
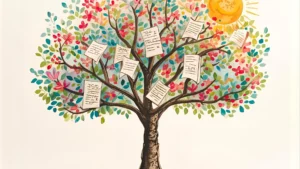
コメント